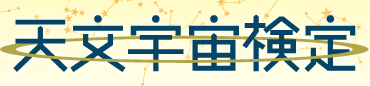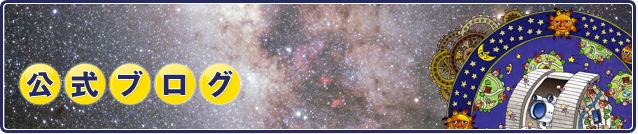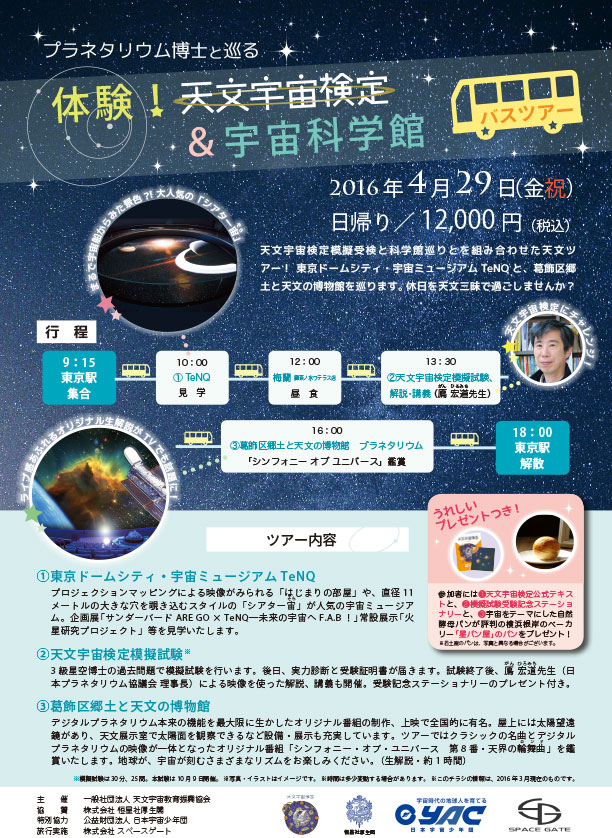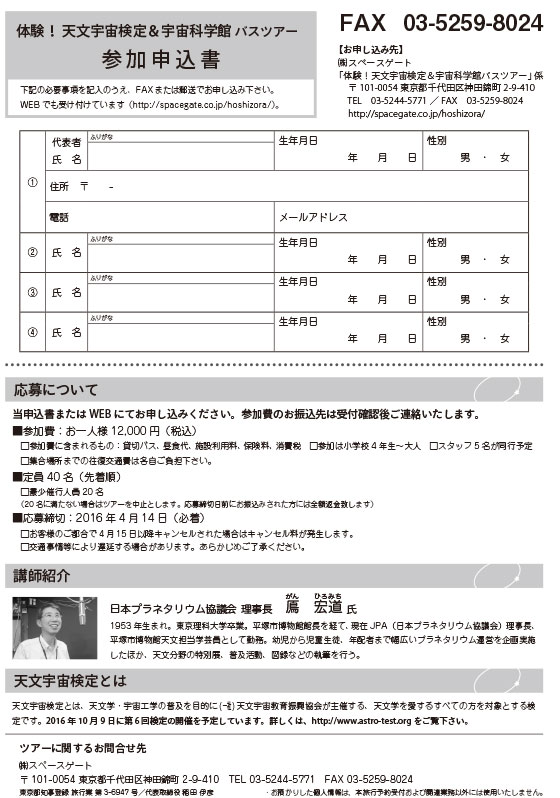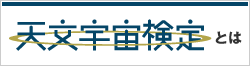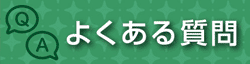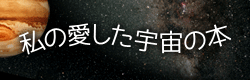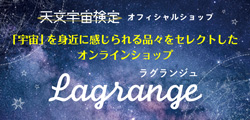第7回天文宇宙検定の試験日まで、
あとひと月と少し。
「どんな問題が出るのかしら?」
「どんな勉強をすればいいのかなぁ?」
という声にお応えすべく、
昨年の合格者の皆様から頂いたアンケートから、
その内容の一部をご紹介させていただきます。
これから検定に挑戦される方、ぜひご参考に。
なお、スペースの都合上、
掲載文は、原文通りではありません。
御了承ください。
まず、本日は準1級と1級合格者の方の声。
1級試験は、過去5回開催されましたが、
合格されたのは、いまだ20名足らずです。
「天文宇宙博士」となられた方々には、
天文学に長く親しんでこられた方や、
実は、理工系の勉強をなさってきた方など、
強者揃いといった感がありますが、
みなさん、宇宙が好きという共通点があるようで。
日々の研鑽が実ったという印象です。
アンケート用紙に加えて、
びっしり書き込みされた別紙を添えて、
御回答いただいた方もありました。
御回答いただいた皆様に、
この場を借りて御礼申し上げます。
■準1級合格者:匿名様
検定に向けた学習期間は?
3ヵ月~2か月
1日の平均勉強時間は?
1時間以内
どのような勉強法を行いましたか?
放送大学の「宇宙を読み解く」「宇宙とその進化」を
録画して気になる部分を重点的にチェックし、
ノートにまとめました。
その際、『超・宇宙を解く』公式参考書を活用し、
『公式問題集』を繰り返し見返しました。
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
何から取りかかればよいか悩んだときは、
恒星の進化について勉強すると、
自然と他の分野にも派生して、
芋づる式に覚えられるように感じました。
■1級合格者:ハンドルネーム ごまどうふ様
検定に向けた学習期間は?
6ヵ月~4か月
1日の平均勉強時間は?
1時間以内
どのような勉強法を行いましたか?
テキストを読む。興味ある所から。
雑誌やニュースをみて、疑問点は調べる。
検定対策にオススメの本は?
『基礎からわかる天文学』半田利弘(誠文堂新光社)。
網羅的でわかりやすいと思います。
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
好きなところから始めるのが一番だと思います。
■1級合格者:ハンドルネーム TAKU様
検定に向けた学習期間は?
3ヵ月~2ヵ月
1日の平均勉強時間は?
2時間以上
どのような勉強法を行いましたか?
『超・宇宙を解く』、『1級公式問題集』3冊、
『2級公式問題集』2冊から、
過去問のレジュメを作っての精査、精読。
検定対策にオススメの本は?
『現代の天文学シリーズ17巻』岡村定矩 他(日本評論社)
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
諦めずコツコツやれば、通ります。
■1級合格者:匿名様
検定に向けた学習期間は?
6ヵ月~4ヵ月
1日の平均勉強時間は?
1時間以内
どのような勉強法を行いましたか?
『超・宇宙を解く』・『公式問題集』を読んで解きました。
苦労したことは特になく、楽しんで勉強できました。
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
理解できるまで、問題を多方面から検討するとよいと思います。
■1級合格者:越ケ浜六区様
検定に向けた学習期間は?
3ヵ月~2ヵ月
1日の平均勉強時間は?
2時間以内
どのような勉強法を行いましたか?
『超・宇宙を解く』や『公式問題集』を通読はした。
その他の天文関連の書物を購入し、できるだけ読むようにしました。
全くの独学であることに苦労しました。
検定対策にオススメの本は?
『最新天文百科』(丸善出版)
『完全独習現代の宇宙物理学』(講談社)
『新天文学辞典』(講談社)
『完全図解宇宙手帳』(講談社)
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
テキスト以外の本からの知識を習得することで、
より理解が深まる。
天文ニュース等で最新情報を得る。
■1級合格者:匿名様
検定に向けた学習期間は?
6ヵ月以上
1日の平均勉強時間は?
30分以内
どのような勉強法を行いましたか?
1年を通じて公式参考書を読み込む。
過去問題を解き直す。
『新天文学辞典』(谷口義明監修・講談社ブルーバックス)を読み切る。
「天文ガイド」「星ナビ」を毎月購読。
試験1ヵ月前は、国立天文台・アストロアーツの
トピックス記事等を拾い読みする。
新聞の天文関係記事があればスクラップする等。
一通りの物理学の基礎は学んでいたので、
読み込むのに「何が書いてあるのかさっぱりわからない」ということはなく、
理解しながら読み進めることができた点が大きかったのではないかと思う。
これから検定の勉強を始める方へメッセージ
1年で合格しようとせずにマイペースで勉強することだと思います。
興味が続けば必ず合格します。
続けているうちに自分が理解している得意分野も広がり、
毎年受ければ「試験問題の当たり年」にも出会います。
明日は、2級のアンケートをご紹介する予定です。
試験後に開催した「答え合わせ会」や、メール等で、
いくつか御質問をお寄せいただきましたので、
御回答、および補足説明をいたします。
■【質問1】
2級問39は、②も正解なのでは?
【2級 問39】
固体ロケットと比べたときの、液体ロケットの利点は何か。
①開発コストが小さい
②大きな推力が得られる
③燃焼の中断、再着火ができる
④燃料を充填したまま長期保管ができる
【正解】
③
【解説】
以下の表のように、
固体ロケットと液体ロケットの双方に利点と欠点がある。
例えば、
H-ⅡAロケットは、液体水素と液体酸素を推進剤とした
液体ロケットであるが、
搭載重量に応じて固体補助ロケットを追加するなど、
双方の利点を活用している。

【補足説明】
「推力」と「比推力」は、混同しがちなので、
本問はまぎらわしい問題だったかもしれません。
上に挙げたのは解答速報からの抜粋です。
解説文中の『2級テキスト』図表9-1では、
液体ロケットと固体ロケットの「比推力」は比較していますが、
「推力」については比較されていません。
『2級テキスト』傍注(P.124)にある
「液体ロケットの方が燃焼効率はよいので、
比推力や噴射速度は高くしやすいが、
推力は固体ロケットの方が高くしやすい」
という記述等が正答を選び出すカギとなります。
まず、「推力」とは何かを考えましょう。
推力とはロケットを進行方向へ推し進める力で、
ロケットから毎秒噴射される燃焼ガスの質量と
燃焼ガスの噴出速度の積に比例します。
単位はN(ニュートン)です。
1Nは1kgの物質に1m/s² の加速度を
生じさせる力をいいます。
「推力」の大きさにおいて、
液体ロケットは固体ロケットに及びません。
具体的に推力の絶対値を比較すると、
以下とおりです。
【液体ロケットの例】
スペースX ラプター・・・・・・ 3050 kN(キロニュートン)
スペースシャトル SSSE・・・・・・ 1860 kN(キロニュートン)
【固体ロケットの例】
スペースシャトル固体ブースター・・・・・・ 12500kN(キロニュートン)
M-Vロケット M-14・・・・・・4214kN(キロニュートン)
H‐ⅡAロケットにおいても、
第1段のメインエンジン(液体)の推力は、
真空中およそ1100KN(キロニュートン)ですが、
両脇についている固体燃料ロケットの推力は、
1本あたりおよそ2500KN(キロニュートン)もあります。
つまり、
「②(液体ロケットは固体ロケットより)
大きな推力が得られる(利点がある)」
とはいえないので、②は不正解となります。
ちなみに、「比推力」で比べると、
液体燃料ロケットの方が大きいです。
『2級公式テキスト』(P.124・125)にあるように、
「比推力」とは、発生する推力を
1秒当たりの推進剤消費量で割ったもので、
推進剤の性能を示すものといえます(単位は秒で表します)。
つまり、比推力とは、
単位質量の推進剤が単位質量の推力を何秒間出せるか、
と言い換えることもできます。
H‐ⅡAロケットの場合、
第1段メインエンジン(液体)の比推力は約440秒、
両脇の固体燃料ロケットの比推力は約283秒であり、
液体燃料ロケットの方が大きくなります。
選択肢②が
「②(液体ロケットは固体ロケットよりも)
大きな比推力が得られる」であったならば、
正解は②と③となりましたが、
設問では、「推力」とありますので、
③のみが正解となります。
■【質問2】
2級 問7
「あなたは宇宙初期に銀河をつくることにした。
必要な材料の組み合わせで正しいものはどれか」とありますが、
「あなたは宇宙初期の銀河を~」ではないでしょうか?
【回答】
問題制作者の意図を尊重したものですので、
ご理解いただきたくお願いします。
ご指摘の文章であっても設問の正誤に
影響を及ぼすものではないと判断いたします。
■【質問3】
公式テキスト3級 2015~2016のページ112、ほぼ真ん中の、
アメリカ 月探査機サーベイヤー1号の年は1965ではなく、
1966ではないでしょうか?
そうしませんと、上下の年と釣り合わない気がします。
「恒星社恒星閣」さん発表の誤記表にありません。
【回答】
大変失礼いたしました。誤植です。
公式ホームページの正誤表に追加をいたしました。
訂正してお詫び申し上げます。
○第5回天文宇宙検定受験者データ
第5回天文宇宙検定(2015年10月11日開催)
●最年少受験者
6歳
●最高齢受験者
91歳
●受験者男女比率
1級 : 男性 89 %、女性 11 %
2級 : 男性 66 %、女性 34 %
3級 : 男性 52 %、女性 48 %
4級 : 男性 55 %、女性 45 %
●合格率
1級 : 3.2%
準1級 : 7.9%
2級 : 5.7%
3級 : 65.8%
4級 : 64.1%
●最高得点
1級 : 78点
準1級 : 68点
2級 : 85点
3級 : 96点
4級 : 100点(2名)
●平均点
1級 : 45.7点
準1級 : ――点
2級 : 51.8点
3級 : 64.5点
4級 : 66点
○第5回天文宇宙検定講評
■ 4 級
昨年と比べて平均点、合格率はほぼ変わらなかった。
受験者は例年通り10代、10歳以下が多かった。
親子での受験も増えており、各試験会場では家族で『公式テキスト』を読みながら、
最終確認をしている姿がよく見られた。
正答率がもっとも低かったのは、
【問28】一番多く隕石を保有している国を問う問題(正答率26.0%)であった。
選択肢②のロシアを選んでしまった受験者が多く、
2013年にロシアのチェリャビンスク州に落下した隕石を
覚えている人が多かったためではないかと思われる。
二番目に低かったのは、【問11】三大流星群ではないものを選ぶ問題(正答率26.2%)。
選択肢④のしぶんぎ座流星群を選んでしまった受験者が多かった。
しぶんぎ座流星群は1月4日頃の夜明け前に多く見られるが、
今年は月明かりがあり観望の条件が良くなかったため、
印象に残らなかったのかもしれない。
続いて【問30】写真からりょうけん座M51を選ぶ問題(正答率34.8%)、
【問10】太陽の赤道付近の自転周期を問う問題(正答率36.2%)、
【問34】地球から土星の輪が見えなくなる年を問う問題(41.7%)の正答率が低い。
正答率が高かったのは、
【問38】天体とは呼べないものを選ぶ問題(正答率98.1%)、
【問26】地球にクレーターが少ない理由を問う問題(正答率94.8%)、
【問20】宇宙服を着る理由を問う問題(92.5%)、【問25】地球の自転についての問題(正答率89.2%)、
【問3】日本で一番夜が短い日を問う問題(正答率85.9%)であった。
一方、【問7】星座早見ばんの東西南北の組み合わせを問う問題(正答率56.6%)や、
【問13】銀河系の中心は地球から見てどの星座の方向にあるかという問題(正答率69.1%)などは、
過去問題や『公式問題集』に掲載されたものとほぼ同じ問いだが、正答率が低かった。
過去問題をしっかり復習しておけば、合格につながるだろう。
■ 3 級
出題数が多いことによる解答時間不足を訴える声に応えて、
今回より出題数を60問に減じた。
その影響が心配されたが、3級合格率は65.8%で、
前回と比較するとマイナス1.3%にとどまった。
受験者アンケートにも時間が足りないという声はほぼなくなった。
正答率が低かった問題は、
【問55】日本で初めて反射望遠鏡を制作し、天体観測を行った人物を問うもの(正答率16.0%)、
【問37】史上初の彗星着陸を果たした探査機を問うもの(正答率16.6%)、
【問53】磁場がほとんどない惑星を問うもの(正答率17.7%)、
【問58】「ロケットの父」と呼ばれた人物を問うもの(正答率27.4%)、
【問50】世界にいくつかある宇宙創世神話でヌンなる世界からアトゥムが誕生した神話が
どこの神話かを問うもの(正答率30.1%)等である。
試験問題はすべて『公式テキスト』の記述から出題されるので、
しっかりと読み込んで試験にのぞまれたい。
正答率が高かった問題は、
【問19】白夜について正しい説明を選ぶ問題(正答率96.9%)、
【問12】虹について正しく述べているものを選ぶ問題(正答率95.5%)、
【問42】自ら輝いている天体の名称を選ぶ問題(正答率94.8%)、
【問49】日本で古くから「ナナツボシ」と呼ばれている星の現在の名前を問う問題(正答率94.8%)、
【問34】黄道は天球上におけるどの天体の通り道かを問う問題(正答率94.4%)などである。
いくつかサービス問題ともいえるような問題があるのはご愛嬌として、
正答率が9割を超えた問題には、天文学の初学者に知っておいてほしい
基礎知識について問うものが多かった。
これら知識は今後必ず、本を読むときやプラネタリウムへ出かけたときなどに、
何も知らない頃よりも広い世界を見せてくれる手助けになるはずである。
合格するためのアドバイスとしては、
例年、応用力を試される計算問題が数題、必ず出題されるので、
主な天体の大きさや距離などは覚えておくと解答に早く辿りつけるだろう。
また、天文学史に関する問題も同様で、
様々な天体現象の謎を解き明かした科学者にも
興味を持ってもらいたいと思う。
■ 2 級
3級同様に60問に出題数が減じられて初の試験であった。
2級の合格率は過去、23.7%(第3回)、20.0%(第4回)と推移していたが、
今回の合格率は5.7%と、前回比マイナス14.3%と大幅に下がった。
大きな原因として考えられるのは、
出題数の減少によって、応用力を試す粒選りな問題が
多く採用されたことによるものと考えられる。
点数分布をみても、50点台が受験者の33%を占めており、
平均点51.8点は、例年よりも10点近く下がっている。
今後の試験問題選考に一石を投じる結果となった。
2級合格のためには、
『公式テキスト』の記述に基づく応用問題に対応できる力をつける必要がある。
これは付け焼刃で養えるものではなく、
『問題集』や公式ホームページで公開されている過去問題などで、
じっくりと取り組んで理解を深めていただくより他ないと考える。
アンケートでは「どのように勉強したらよいかわからない」という声や、
勉強会の開催を求める声が多く寄せられた。
今後の課題として検討を進めたい。
正答率が低かった設問は、
【問23】水星の公転軌道半径には、近日点と遠日点で、
およそ何キロの差があるか求める問題(正答率15.7%)、
【問4】緑色に見える恒星がほとんどない理由を問う問題(正答率15.8%)、
【問30】惑星の大気スペクトル図の特徴から推測可能な項目を選ぶ問題(正答率15.8%)、
【問46】活動銀河に関する記述から間違っているものを選ぶ問題(正答率23.3%)、
【問1】ドレークの式に含まれない項目をたずねる問題(正答率24.1%)などである。
ケプラーの法則を用いる計算問題などの定番問題は、
過去問題を解くのが理解の早道であろう。
正答率が高かった問題は、
【問55】実用化されているロケットを選択する問題(正答率91.6%)、
【問11】ダークマターとダークエネルギー以外の通常物質が
宇宙に占める割合をたずねた問題(正答率88.2%)、
【問27】銀河系はハッブルの分類のうち、
どの形態に属するかをたずねたもの(正答率85.4%)、
【問56】原始地球の環境と当時生息していた生物の特性を問う問題(正答率82.7%)、
【問19】糸川博士のペンシルロケットの実験の歴史を問う問題(正答率81.5%)などである。
宇宙工学系の問題に強さがみられるのは従来と変わらない傾向であった。
■ 1 級
今年より、1級受験者のうち60点以上を獲得した方を
準1級として認定することとなった。
準1級の合格率は7.9%、1級の合格率は3.2%。
今回の試験の最高得点は78点であった。
過去の最高得点を振り返ると、
71点(第2回)、73点(第3回)、77点(第4回)と推移している。
残念ながら、今年も女性の合格者は出なかった。
正答率の低かった問題は、
【問33】惑星状星雲を形成した恒星の質量について問う問題(正答率11.1%)、
【問1】銀河の各種観測量の間に見られる経験的相関について問うもの(正答率14.3%)、
【問10】Ⅰb型超新星、Ⅱ‐P型超新星、Ⅱ‐L型超新星から
爆発機構が異なるものを選ぶ問題(正答率17.5%)、
【問17】シリウスBの発見者を選ぶ問題(正答率20.6%)、
【問36】潮汐力について正しく解説している文章を選ぶ問題(正答率20.6%)
などである。
正答率の高かった問題は、
【問27】最初に発見された中性子星が属する星座を問う問題であったが、
本問は選択肢に正解が含まれていなかったため全員を正解とした(正答率100.0%)、
【問23】パルサー発見時のエピソードと電波放射メカニズムを問う穴埋め問題(正答率93.7%)、
【問21】満月の表面輝度とレゴリスの関係に関する問題(正答率79.4%)、
【問39】生命起源に関するパンスペルミア説について正しいものを選択する問題(正答率77.8%)、
【問13】渦巻銀河の円盤部の回転運動を調べる分光観測について問うたもの(正答率74.6%)。
■ 総 括
本天文宇宙検定は、宇宙のはじまりから生命の誕生まで、天文や宇宙に関わるあらゆるテーマについて、
知識や理解を深めていって欲しいというねらいがある。ただし、項目の内容や現象の数値を暗記するの
ではなく、その意味を考えて意外な気づきを見いだして欲しい。たとえば、太陽の表面温度は6000Kとい
う記述があったとして、その値は覚える一方、そんな高温だと何が燃えているのだろうかと考えてみて欲し
い。別の場所では太陽がほとんど水素ガスでできていると書いてあるだろうし、太陽の中心部では核融合
反応で莫大なエネルギーが発生していると書いてあるだろう。これらをつなぎ合わせていくと、太陽の表
面ではそもそも燃えるものはなく、太陽表面のガスがただただ熱い高温ガスであるに過ぎないことがわか
ってくるだろう。そういう理解が進むと、空に仰ぎ見る太陽がまた違ったモノに見えてくると思う。
またテキストを読む際には、内容を暗記したり、その意味を理解するだけでなく、具体的な数値は自分の
手を動かして確認して欲しい。たとえば、太陽の質量は2×1030kg、半径は70万km、平均密度は
1.4g/cm3などという数値が書いてあったとしたら、実際に電卓を叩いて、太陽の半径から太陽の体積を
計算して、太陽に質量を体積で割って、平均密度の値を自分でも計算してみて欲しい。たんに丸暗記
するよりは、そのような作業を通した方が、数値なども頭の中にしっかり刻み込まれるだろう。数式や公式
なども、テキストの字面を追うだけではなく、自分の手で紙に書いてみて欲しい。数式は敬遠されがちだ
が、自分の手できちんと書き出してみれば、多少は可愛くみえてくるかもしれない。
今回、3級と2級の出題数を減じたにもかかわらず、3級の合格率は平年並みだったが、2級の合格率が
大きく下がってしまった。クラスが上がるほど、より宇宙を深く理解するためには、思考力や計算力が必要
になってくる。数学の問題と思わずに、自然の仕掛けたパズルを解くつもりで、宇宙の計算もしてみて欲しい。
2015年12月吉日
天文宇宙検定委員会